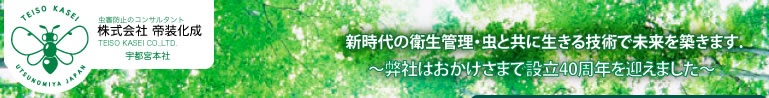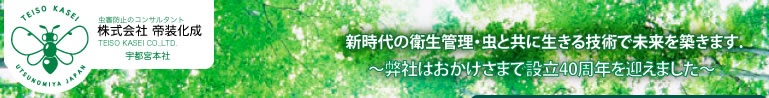| |
|
| |
| |
晩秋の頃になると、成虫が越冬場所を求めて家の中に入ってきます。特に林地や森などの付近にある住居では多数侵入してくることが多いようです。
問題となる種としては、クサギカメムシ、スコットカメムシ、ツマジロカメムシ、マルカメムシなどが知られています。
なぜ臭いかですが、カメムシは外部から刺激があった時にだけ、臭いを放ちます。この臭いは後胸腹面にある臭腺から分泌されるもので、本来は捕食者に対しての防御のために発するものです。ですからつかんだりして刺激を与えなければ臭いを発することはほとんどありません。たいていはカメムシがいるからといって排除しようとして触ったり箒で掃いたりして刺激を与えた結果、くさい臭いで部屋が充満してしまうというということでしょう。 |
| |
| |
 |
| |
1.お申し込み(お問い合わせ)
お電話(フリーダイヤル0120-45-1973)、メール、FAXなどにてお申し付けください。
担当者が詳しい状況を聴き取りにて調査させていただきます。 |
| |
2.現場調査・お見積もり
担当者が直接現場に伺い、状況を確認します。状況確認後、施工内容のご説明と併せてお見積もりを提出させていただきます。
もちろん調査・お見積もり提出は無料で行っております。 |
| |
3.防除
現在侵入している個体の駆除、侵入を阻止するための薬剤塗布をその場所に合わせた形で行います。 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
自然界ではテントウムシは越冬するとき、石や倒木などの物かげで、数匹〜数十匹の集団を作ります。しかしながらより気象の変化をうけにくく、安定した環境である人の住居周辺は彼らにとって格好の越冬場所として選ばれたのでしょう。雨戸の戸袋や物置の中、軒下や石塀の隙間などが好まれるようです。毎年同じような場所で越冬するという光景を見ることも少なくありません。越冬のために集団で移動することもしばしばあるため、移動中の集団を見た人は何事かと思うでしょう。
問題となる種としてはナミテントウが代表的です。この種は体色や斑紋の変異に富んでおり、黒地に2つの赤い紋、黒地に4つの赤い紋、赤や黄色に多くの紋、赤や黄色の無地など多くの型が知られています。よくいろいろなテントウムシが侵入しているということがありますが、多くの型があるナミテントウ1種類である場合がほとんどです。テントウムシの代表種であるナナホシテントウはススキの株元などで越冬することが知られており、集団をつくることはほとんどありません。
テントウムシもカメムシ同様、臭いを発します。テントウムシは外部から刺激をうけると関節部から黄色い液体を出します。これが臭いを発します。本来は鳥などの外敵に対する防御のためのものですが、人の住む空間に侵入したとき、排除しようとして手で払ったり、箒で掃いたりすると臭いを発することとなります。 |
| |
| |
 |
| カメムシ防除とほぼ同じです。状況によって処理薬剤が異なることがあります。 |
| |
| |